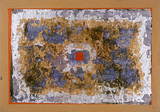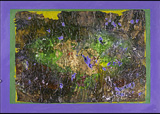(まことの恋をする人はみな一目で恋におちる)
三辺律子
見たとたん、訳したいと思ってしまった。ジャン・ベルト・ヴァンニさんの手がけた絵本『love -ラブ-』。最初は、その個性的なデザインに目を奪われた。ページのあちこちにあいた穴、めくるたびに変化していく切り抜きの妙、大胆だが計算しつくされた色使い、微妙な色合い。一目ぼれだった。
けれど、編集者の方に頂いた本を何度も読み返しているうちに、また別の魅力が立ちあがってきた。孤児の女の子のどうしようもない寂しさ、決して感傷に流れない切なさがひしひしと胸に迫り、気がついたら完全に恋に落ちていた。ヴァンニさんのイラストは、絵本につけられた文字に負けず劣らず、女の子の孤独を物語っていた。
子どもが絵本を好むのは、当たり前のように思われているけれど、改めて考えてみると、イラストレーションというものの特質が浮かびあがる。著名な絵本作家のロジャー・デュボアザンが、絵画(ペインティング)に対するイラストレーションを「文章の助けなしに物語を語る―――つまり、絵による文学」だと述べているが、つまり、文字を読めない(あるいはすらすらと読めない)子どもにとって、イラストレーションはまさに物語そのものなのだ。
ヴァンニさんのイラストは、雄弁に物語を語る。ページにあけられた窓(穴)の奥にポツンと立っている女の子。白と黒で描かれた大勢の子どもが遊ぶ孤児院の風景では、女の子のいるところだけがオレンジ色に切り抜かれている。女の子の運命が坂道を転げ落ちるように暗転していく場面では、ページが細く切り刻まれ、不安を募らせながらページをめくる読者の手も自然と速くなる。そんなヴァンニさんのイラストのテクニックに、わたしは完璧にノックアウトされてしまったのだ。
とはいえ、好きという感情はそう簡単には説明できないのが常。
物語る絵であるイラストレーションに対し、絵画(ペインティング)は「感覚に達することだけを意図」したものであり「感じられるだけであって、言葉では表現されえない」。デュボアザンは、絵に必ず文学性を見出そうとする傾向を憂いたドラクロアの考えを紹介して、そう定義しているが、わたしの一目ぼれを説明してくれるのは、まさにこれだと思う。ヴァンニさんの作品は見たとたん、わたしの「感覚に達した」から。
『love -ラブ-』の絵画的側面に一目ぼれして、イラスト的側面に陥落-――わたしの恋心(?)を無理に言葉にすればそんなところかも。
だから、〈ときの忘れもの〉のヴァンニさんの展覧会に出かけていったわたしが、再び一目ぼれを喫し、ヴァンニさんの絵をどうしても我が物にしたくなってしまったのも当然の結果だった。今、自宅のリビングの一角に飾ってあるその絵を見るたびに、ヴァンニさんの作品への恋心をますます募らせている。そして、81歳というお年を感じさせない精力的な、日本を愛する紳士ヴァンニさんご自身にも!
2008年4月 (さんべ りつこ)
*下記の図版は、『love』の英語版より。




*3月14日のオープニングの折、三辺さんとジャン・ベルト・ヴァンニさん。この日お二人は初めて会った。
『love -ラブ-』
著者: デザイン&イラスト/ ジャン・ベルト・ヴァンニ
ストーリー/ ローウェル・A・シフ
訳/ 三辺律子
青山出版社
B5判変型(225×124)
角背上製 76ページ
価格: 定価1,890円(税込み)
(ヴァンニさんのサイン本が画廊に少し残っています。)
◆三辺律子(さんべりつこ)
東京生まれ。英米文学翻訳家。白百合女子大学大学院児童文化学科修了。
主な訳書に『よにもふしぎな本をたべるおとこのこのはなし』オリヴァー・ジェファーズ(ヴィレッジブックス)、『龍のすむ家Ⅲ 炎の星』クリス・ダレーシー(竹書房)、『魔女の愛した子』マイケル・グルーバー(理論社)、他。
*画廊亭主敬白
3月に開催したジャン・ベルト・ヴァンニさんの『love -ラブ-』出版記念展への「コレクターの声」は、『love -ラブ-』を翻訳された三辺さんが執筆してくださいました。
タイトルは、翻訳家らしくシェイクスピアの『お気に召すまま』から。マーロウの詩からシェイクスピアがとったそうです。
『love -ラブ-』は1964年にフランスで出版され、世界中で100万部以上のロングセラーになっている本ですが、物語としても、見て楽しむものとしても、一度味わえばきっと人にも勧めたくなる、そんな素晴らしい体験を与えてくれる絵本です。
今回の展覧会にふさわしい素敵なメッセージを三辺さん、ありがとう。