◆浮田要三展
会期=2016年4月8日[金]―4月23日[土] 12:00-19:00
※日・月・祝日休廊
 |
|
1954年に関西在住の若手作家を中心に結成された「具体(具体美術協会)」。1950年代にはまだパフォーマンスやインスタレーションといった表現が新奇の眼で見られるだけで、美術作品としての評価はなかなかされにくい時代でした。
しかし近年では国際的にも注目をあび、1950~70年代の日本のアートを再評価し検証する動きが活発です。2013年2月にニューヨークのグッゲンハイム美術館で開催された「GUTAI」展は大反響を呼びました。
具体のリーダーであった吉原治良の「人の真似をするな」という言葉に象徴されるように、具体美術協会に参加した作家たちは従来の表現や素材を次々と否定して新しい美術表現を旺盛に展開していきました。
本展では「具体」に参加した浮田要三に焦点を当て、油彩作品をご覧いただきます。
■浮田要三 Yozo UKITA(1924-2013) 1924年大阪生まれ。1955年以降、吉原治良主宰の「具体美術協会」に参加。1964年、具体美術協会を退会。2013年逝去、享年89。
~~
浮田要三の言葉
人間とは、悲しみの塊である。
その哲理を体得して、行為する作品を制作する。
それが正に「生」そのものと考える手段ではない。
生きている證としての作品の制作こそが、人間の本業と心得て
生ある限り生きるべきだと思っている。
『浮田要三の仕事』(2015年、りいぶる・とふん発行)より
~~
「浮田要三展に寄せて」
河崎晃一
(甲南女子大学文学部メディア表現学科教授)
※河崎晃一さんの名前表記について
「崎」は旧字ですが、パソコンによっては文字化けする恐れがあるため「崎」で表記しています
浮田要三のいろとかたち
赤、濃紺、青、黄、ピンク・・・色彩のシンプルな選択による作品は、浮田が楽しみながらかたちと色を置いていった痕跡である。支持体となる布にコーヒー豆の袋などに使われるドンゴロスを用いて、それを切ったり、折り曲げたり屈託のない表現が作品を見る側の受け皿を広げていってくれる。ドンゴロスには、たっぷりと油絵の具が塗られている。それらは描かれたものではなく、切り絵のように色付けられたドンゴロスのコラージュである。重みを感じさせる素材はさまざまな表情を見せてくれる。素材が主人公となる作品は、とかくマンネリ化した作風になりやすいが、浮田の作品にはそれがない。一つ一つの作品と対話できる可能性が潜んでいるように思う。
そのような一般的な作品への視線を批判するように「最近、ボクは絵画的な要素(点・線・色彩・構成など)をそれ程重要視しておりません。」(注1)と浮田は、否定する。絵画的な判定を「思考的に力が薄らぎます」(注2)とその正体を考えることではなく、感じることではないかという。「感性への想い」から自身の存在を見出そうとしている。絵は理屈や説明ではないということなのだろうか。
浮田要三と『きりん』
画家としての浮田要三(1924~2013)の活動は、具体美術協会時代の1955年から64年までと1983年から亡くなる2013年までの時期に分かれる。しかし、画家としてよりも浮田の純粋な心の基盤を支えたのは、児童雑誌『きりん』の編集者として活動したことであった。『きりん』は1948年2月大阪の尾崎書房から創刊された子どもの詩と絵の雑誌であった。その営業、編集実務を浮田ともうひとり星芳郎が担当、子どもから寄せられる詩の選者は、当時毎日新聞大阪本社に勤務していた井上靖、彼はまさしく『きりん』の生みの親であった。そして毎日小学生新聞で詩の選者を務めていた詩人の竹中郁が携わり、さらに足立巻一、坂本遼が加わり編集体制ができた。そこでの浮田の役割は、近畿一円の小学校を訪れ、国語の授業の副読本として勧め、時には子どもを集めて詩の朗読をしたという。1962年に廃刊となるまでの14年間に浮田が『きりん』から教えられた事柄は、浮田の生き様を示すものであった。
創刊号の表紙絵は、脇田和が手がけ、次にのちに具体美術協会の代表となる吉原治良に表紙絵を依頼したのは、3号目であった。編集者は、創刊当初から『きりん』とのなんらかの関わりを吉原に求めていたのである。この出会いが、浮田のその後の芸術観に大きな弾みを与えた。その後も表紙絵は、小磯良平、須田剋太、山崎隆夫らが手がけているが、子どもとの絵のかかわりに深く関わっていったのは吉原であった。この時点で浮田は、まだ絵画を手がけてはいない。編集者、販売営業マンとして東奔西走していたのである。そして毎月推薦されてくる子どもたちの絵を選び、それを表紙絵やカットとして使った。多く寄せられる詩とともに子どもたちの純粋な表現を見ることは、浮田の芸術観を形成し、芸術家でもない、芸術批評家でもない浮田要三を生み出した。
吉原治良と浮田要三
子どもの絵、詩を通じて直感的に生まれてきた浮田の眼は、吉原との出会いによって急速に膨らみ、ふたりは接近していった。吉原にとっても子どもの創作力は関心を寄せるところであり、1948年には第1回阪神童画展覧会を企画し未就学児童の絵を中心に公募した。この展覧会は、「童美展」として具体メンバーたちの審査によって2008年まで58回続けられた。吉原は、子どもの絵に魅せられ『きりん』の挿絵、文章を引き受け、たびたびその名を見ることができる。1953年ころからは、のちの具体メンバーとなった嶋本昭三の名も登場し、吉原を通じての交流の広がりが見て取れる。一方で1955年12月に開催された『きりん』発行所(日本童詩研究会)の主催による「きりん展」は、具体メンバーたちが指導してきた中学生以下の子どもによる図画工作の公募展だった。審査には、吉原治良、須田剋太らがあたり、具体の嶋本昭三、山崎つる子、金山明、田中敦子、白髪一雄、村上三郎が徹夜で展示をしたという。この経験は、彼らにとって子どもの自由な表現力を強く感じ取った出来事であった。初期具体メンバーたちの何人かは、子どもたちに絵を教えていた。そして「きりん展」「童美展」に携わることによって、彼らは創作の大きな刺激を受けていたのである。その仲間に浮田の存在がったと考えられる。浮田には、具体美術協会に所属した作家の中で、参加したきっかけ、その経歴、関わり方など他の作家とは大きく異なるところがある。浮田が具体の創立の時、最も貢献したのは、機関誌『具体』の第1号の印刷であった。メンバーは、浮田が提供した印刷機を嶋本のアトリエに持ち込み編集制作した。1955年、吉原から具体のメンバーになることを勧められた浮田は、初めて絵画を制作するという未知の世界に足を踏み入れた。それは、何よりも吉原の浮田への最大の評価であり、信頼であったと言えるだろう。「ところが実際に制作を始めますと、作品の良し悪しが全く分からず」(注3)と当時の心境を記している。しかし、本人の価値判断が定まらないまま、素材を意識した1958年の「新しい絵画世界展アンフォルメルと具体」の出品作は、吉原も認めるところであった。「自分では分からないのに、他人の吉原先生がほめて下さるというのは、うれしいことでありましたが」(注4)とその戸惑いは隠せない。そして自身の判断で1964年に具体を退会することになる。そこには、浮田の芸術評価に対する毅然とした態度が示されている。
画家浮田要三
浮田が制作を再開したのは1983年だった。実際には制作から離れていたのは退会後10年ほどで、75年ころからは解散後の具体メンバーとの交流もあり少しずつ制作を始めていた。そのブランクを知りながら浮田を誘ったのは嶋本昭三だった。嶋本はデュッセルドルフで開かれた「具体AU6人展」(注5)の現地制作に浮田を誘い、その経験は浮田の創作意欲を蘇らせた。このきっかけ作りは、嶋本たちが浮田の才能を信じ、彼自身にそのことを認識させるきっかけ作りだったのかも知れない。画家浮田要三は、50年代半ばから10年足らずの助走、そしてブランクを経てこの時はじめて自他ともに認める存在となったのではないだろうか。ただ、現代美術と呼ばれるジャンルの若い世代の台頭とは、全く異次元の表現であり、制作に対する考え方は、より深く、地に足が着いていて哲学的である。元具体メンバーの画家というより、具体の精神を表面下で継承する浮田要三の名が相応しいように思う。具体時代に吉原から学んだ芸術に対する精神は、そこにしっかりと受け継がれていた。
1998年4月、浮田はフィンランド、フォルッサの画家協会の招待を受け妻とともに約1年間滞在することになる。現地の新聞の取材に「新しいものを求めてやってきた」と意欲を見せている。浮田73歳の時である。夏は短く厳冬の地フィンランドでの生活は、どのようなものだったのだろうか。近年の北欧ブームとはかけ離れた浮田の姿が浮かぶ。1年後の成果をフォルッサの美術館(注6)で個展を開催、その時のパンフレットは「ほとんどなにもない作品集」と名付けられた。浮田の自然体の生き方がなにもない状態に例えられ、彼の生活そのものが作品に通じていることは、人間味を感じさせる。
70歳をすぎてからの浮田の制作意欲は、年を追って活発、意欲的になる。展覧会歴を見ていくと1994年の初個展から亡くなる2013年まで、多い時には年3、4回の個展を開催している。この約20年が画家浮田要三の真価を問われる時代である。浮田の作品群とその生き方、精神など内面的な事柄を結びつけながら浮田要三を見ていくことはたやすいことではない。しかし、浮田自身も言うように、作品は感じ取るものであり理屈はいらない。それを教えてくれる作品である。
浮田要三に関しては、これまでに出版された作品集『浮田要三の仕事』に浮田本人の文章「浮田要三小論(哲学的考察に於いて)」とともに、浮田を敬愛する4人の研究者、学芸員、作家によって論じられている。それらは、作品を時代順に追って見るだけではなく、浮田要三を知ること、彼自身がどのような姿勢で制作に向かっていたのか、なによりどのように生きようとしたのかが伝わって来る。
(かわさき こういち)
注釈
注1 「浮田要三小論(哲学的考察に於いて)」、『浮田要三の仕事』、浮田要三作品集編集委員会編、p,13
注2 同上 p,13
注3 同上 p,12
注4 同上 p,12
注5 1976年から嶋本昭三が事務局長を務めるAU(アーティストユニオンから1980年に名称変更)がAtelierhaus Hildebrandstrasse, Dusseldorfにて開催した。1983年6月19日~26日。出品作家は、浮田要三、嶋本昭三、村上三郎、山崎つる子ほか。
注6 The South-West Hame Museum, Forssa, Finland
●図録のご紹介
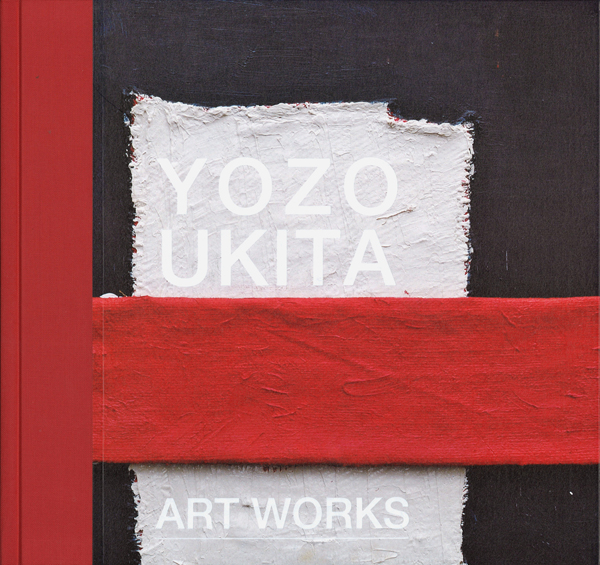
『浮田要三の仕事』
2015年
りいぶる・とふん 発行
316ページ
25.7×27.2cm
価格:10,800円(税込) ※送料別途250円
展示風景
見積り請求(在庫確認)フォーム